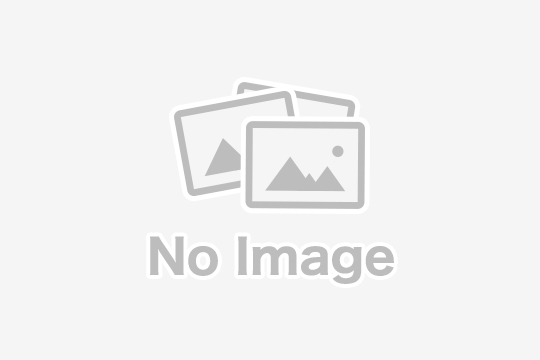最近、林輝太郎さんが書かれた本を色々と読み漁っています。
理由は、何かの記事に林輝太郎さんが書かれた本を読んで、取引の仕方が変わり、勝てるようになったというものを読んだためです。
今回は、「ツナギ売買の実践」という本を読んだ感想です。
林輝太郎(著)
ツナギって、いうのは聞いたことはあるんですがいまいちツナギをやる意味がわからなかったので、この本を読んでみることにしました。
ツナギって、例えば現物でA株1000株持っていたとして、A株を信用売りで1000株売る。
これって、A株現物1000株を売るのと何が違うんだろうって思っていました。しかも、現物を売るよりも信用売りのほうが貸株料やへたすると逆日歩までかかり、現物株を売るよりもコストがかかる。
でも、持っている現物株を売るのではなくて、信用売りをする。
それをするメリットが知りたかったわけです。そこらへんについても書かれています。
心理的に非常に楽だから。つまり、利益を得る可能性が高いからだそうです。
この辺の感覚が自分にはまだ完全には理解できていませんが、心理的に非常に楽というのは、投資においてとても重要だということは理解しているつもりです。
やりやすさって投資において、大事なんだなって思うことがあります。例えばですが、証券会社によって、投資成績って変わってくると思います。それは、手数料が無料か無料じゃないかの違いはもちろんあるのですが、例えば、手数料も金利も全く同じでも証券会社によって、投資成績って変わってくると思っています。
これは、最近、玉帖をつけているからわかったことなんですが、本当に、証券会社によって同じ取引を実行しても成績が違ってくるのです。不思議なんですが、これは、心理的に楽とか、やりやすさなんだと思います。それくらい投資ってちょっとのことに左右されてしまうものなんだと思います。
林輝太郎さんの本には事あるごとに、日々、場帖をつけ、値動きを受け止めることが書かれています。はじめは、なんでこんなことをするんだろうって、思いながら毎日場帖を記録していったのですが、やっているうちにだんだんとやる理由がわかってきた。
最近では、場帖も記録していない、値動きを受け止めていない銘柄なんて取引するべきではないとさえ、思っています。それくらい場帖は大事だなと思っています。
これは、やった人にしか絶対にわからないことだと思います。
でも、やってみると本当にいろいろなことが見えてくるっていうか、わかってくる。
株価の値動きなんて、証券会社が提供しているチャートでいいじゃないかって、自分も思っていたんです。でも、場帖をつけてからは、不思議と取引する際に場帖を見て、判断している。
証券会社が提供しているチャートって、なんか変なバイアスがかかるというか、値動きを偏りなしに見れないんです。自分は。多分多くの人が気づいていないだけで、多分そうだと思います。
あと、余計な情報はなくてもいい。逆にあると、邪魔になるのかもしれません。
今の時代だからこを、自分の判断で売買することが大切だと思っています。よくわからないからとか、面倒だからという理由で、AIに任せてしまっている方も多いと思いますが、多くの人がAIに任せているからこそ、自分で判断するべきだとも思います。
あと、かなり前に書かれている本であるということが、逆にこのツナギをやることメリットを物語っています。この本の第1刷発行は1989年。このころの売買手数料や税金はかなりのものだったはずです。おそらく、売買代金の1~1.5%は手数料と今はないような税金を取られていたと思います。
それなのに、ツナギをするということは、それ相応のメリットがあったからに他ならない。通常は、買い、売りで2回、売買手数料を支払うところ。ツナギをして、現渡ではない場合、4回も手数料を支払うことになるわけです。
それだけ、ツナギをやる価値があるということ。今の時代株の手数料は証券会社によっては無料になってきています。これを考えると本当にいい時代に生きてるなと実感します。そのころ、稼いでいた人たちは、現代ではべらぼうに儲けることができるのでしょうね。時代が違うので、それはまた別のはなしなのかもしれませんが。
決算期をまたげば、粉飾できますねの部分。
現在、株の取引で出た利益については、20.315%の税金がかかります。
株の税金って、一度支払うと帰ってこない。損失は繰り越せるけど、前年度の利益とは相殺できない。
例
1年目 100万利益
2年目 100万損失
この2年間だけを見るとプラマイ0なんだけど、203,150円税金が取られる。2年目の損失は繰り越せるけど、1年目の利益とは相殺することができない。
だから、利益を来年に繰り越せるなら、繰り越しておくという考え方。
同一銘柄に売り玉と買い玉とを建てる。決算期末に、利益を圧縮しようとするなら損になってるほうを手仕舞う。益になっている方は翌日(次期期首)に手仕舞えばよい。
利益を繰り越すためだけにクロスをするという発想はありませんでした。上記の問題点は、翌日に窓を開けるような値動きになった場合は損失が出る可能性があります。
◯◯ショックと呼ばれる暴落が起きることなんて、今では当たり前になってきている。自分の利益を守る方法は多く知っているにこしたことはない。
今から30年以上も前に出版された本ですが、今でも使える知識が書かれているので、本当にためになります。この時代の株の手数料は今からでは考えられないほど、高かった。そんな高い手数料を払ってでもやるだけの価値がある方法が考えられている。
この本は、投資をやる方なら一度は読んでおいたほうがいいのではないかと思いました。まだ自分には高度で実践が難しい部分もありますが、とても有益な本だったと思いました。
本のタイトルにも使われているツナギ売買。言い換えるならヘッジ。ヘッジファンドにも使われているヘッジ。投資をやるうえで、必須の考え方なんだろうと思いました。